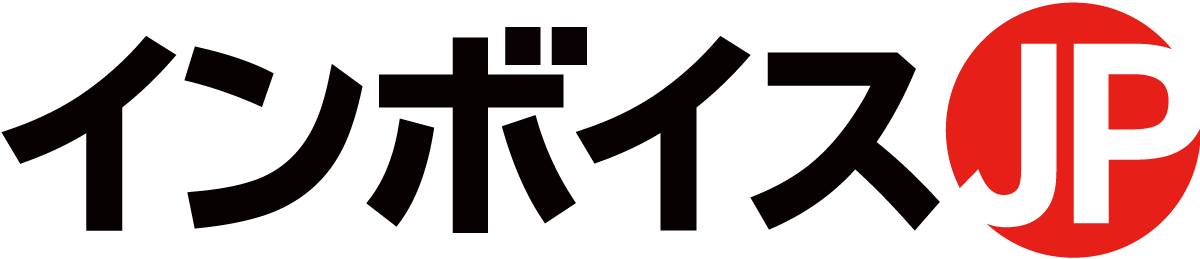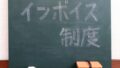2023年10月1日より、インボイス制度が開始されました。
インボイス制度では、これまでと異なる形式の請求書を作成・受領したり、消費税の計算が変化したりするため、経理業務に大きな影響を及ぼします。
インボイス制度導入後もスムーズに経理業務をこなせるよう、然るべき準備を行っておくことをおすすめします。
今回はインボイス制度に伴う経理業務の変化や、インボイス制度のために経理が準備すべきこと、経理業務を効率化するポイントについて解説します。
インボイス制度による経理業務の変化
インボイス制度の導入によって変化する経理業務は5つあります。
適格請求書の作成
自社が適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)である場合、適格請求書(インボイス)を発行する必要があります。
これまでの区分記載請求書では、以下5つの項目を記載する決まりでした。
- 請求書発行事業者の氏名または名称
- 取引年月日
- 取引内容
- 税率ごとに区分して合計した対価の額
- 請求書を受け取る事業者の氏名または名称
一方、インボイスでは上記の項目に加え、新たに以下3つの項目を記載する決まりになっています。[注1]
- インボイスの登録番号
- 適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額など
書類の名称やフォーマット形式は自由ですが、請求書に記載する項目の数や内容に違いがあるため、請求書を作成する際は新たなテンプレートを作成しなければなりません。
請求書の記載項目に抜け漏れがあると、正式な請求書とみなされず、取引先が仕入税額控除の適用を受けられなくなるので注意が必要です。
[注1]国税庁:適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き P16
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022009-090.pdf(参照2023/12/13)
請求書の仕訳作業
インボイス制度導入前までは、発行される請求書は産業にかかわらず区分記載請求書のみとなっていました。
しかし、インボイス制度開始後は、インボイス発行事業者が交付するインボイスと、そうでない事業者が交付する請求書の2通りに分けられます。
このうち、仕入税額控除の適用対象となるのはインボイスのみなので、受け取った請求書はインボイスとそれ以外のもので仕訳して管理しなければなりません。
インボイスを誤ってそのほかの請求書と一緒にしてしまうと仕入税額控除の適用対象外になってしまいますし、逆にそのほかの請求書をインボイスと一緒にしてしまうと税務調査で指摘される可能性があります。
経理はインボイスと区分記載請求書をきちんと仕訳し、混同しないようにする業務を新たに行うことになります。
消費税の計算方法の変更
これまでの区分記載請求書では、消費税の端数処理について、品目ごとに行うことが認められていました。
しかし、インボイスでは取引価額を税率ごとに区分して算出した金額に対して端数処理を行い、消費税額などを計算する決まりになっています。
もし税率ごとに区分した消費税額などに1円未満の端数が発生した場合は、一のインボイスにつき、税率ごとに1回の端数処理を行わなければなりません。[注2]
個々の品目ごとに消費税額などを計算して端数処理を行った場合、先に説明した方法とは異なる結果が出ることがあります。そのため、これまで品目ごとに消費税額などを計算していた場合は、計算方法そのものの変更が必要です。
[注2]国税庁:適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き P17
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022009-090.pdf(参照2023/12/13)
経過措置への対応
インボイス制度開始前までは、請求書を発行したのが課税事業者でも免税事業者でも、受領側は一律仕入税額控除を適用することが可能でした。
しかし、制度開始後は、仕入税額控除が適用されるのはインボイスのみとなります。
ただし、制度開始から6年間は経過措置が設けられており、当初3年間(令和8年10月まで)は免税事業者からの仕入であっても80%を、その後3年間は50%をそれぞれ控除することが可能となっています。[注3]
インボイスを発行できない免税事業者と取引する場合は、請求書の保存と共に、経過措置の適用を受けることを記載した帳簿を保存する必要があります。
また、インボイスとは仕入税額控除の適用率に違いが出るため、計算を誤らないよう注意する必要があります。
さらに三年後には控除の適用率が80%→50%に変化するため、その際の変更も忘れずに適用しなければなりません。
[注3]国税庁:適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き P8
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022009-090.pdf(参照2023/12/13)
インボイス登録事業者の確認が必要
インボイスには、インボイス発行事業者にのみ交付されるインボイス登録番号を記載する項目があります。
前述した仕入税額控除はインボイスにのみ適用される制度なので、受領したインボイスが、正しくインボイス登録事業者によって交付されたものかどうか確認しなければなりません。
インボイス登録番号の検索および確認は、国税庁のインボイス制度適格請求書発行事業者公表サイトにて、登録番号を入力して検索ボタンを押すと結果をチェックできます。
登録番号の検索は一度に10件まで可能で、再度の確認は原則として不要です。しかし手動で検索する必要があるため、複数の事業者からインボイスを受け取った場合、確認作業に手間取る可能性があります。
インボイス対応ソフトのうち、インボイス登録番号の自動チェック機能が搭載されているものであれば、国税庁の定格請求書発行事業者公表システムWeb-API機能を利用すれば、システムに取り込んだインボイスの登録番号を自動でチェックしてもらうことが可能です。
少額取引でも領収書の受領・保存が必要
インボイス制度導入前までは、3万円未満の少額取引に関しては、帳簿への記載をもって領収書なしでも消費税の仕入税額控除が認められていました。
しかし、制度導入後は3万円未満の少額取引でも領収書を受領し、保存しておかなければ仕入税額控除の適用は認められません。
これまで少額取引だからと領収書を受け取っていなかった場合は、領収書の受領および保存を徹底する必要があります。
なお、一部例外として、以下の場合は帳簿に記載・保存すれば領収書がなくても仕入税額控除が適用されます。[注4]
- 3万円未満の公共交通機関の運賃
- 3万円未満の自動販売機および自動サービス機からの購入
- 入場券など使用の際に回収される取引(1の場合を除く)
- インボイス発行事業者でない古物営業者からの古物の購入、質屋からの質物の取得、宅地建物取引業者からの購入
- インボイス発行事業者でない人からの再生資源および再生部品の購入
- 郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出したものに限る)
- 通常必要と認められる出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当など
公共交通機関の運賃および自販機などからの購入に関しては、これまで通り3万円未満でも仕入税額控除の対象となります。しかし、上記のケースに該当せず、かつ運賃や自販機でも3万円を超えた場合は、領収書の受領・保存が必要となるので要注意です。
なお、上記の特例を適用する場合、通常の帳簿の必要記載事項に加え、以下2つを記載する必要があります。
- 帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる仕入に該当すること
- 仕入の相手方の住所または所在地
領収書の受領・保存が必要となるケースが増えたぶん、経理の業務はかさむことが予想されます。
[注4]国税庁:インボイス制度に関するQ&A目次一覧 帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合の帳簿への一定の記載事項 P2
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-14.pdf(参照2023/12/13)
インボイス制度に対して経理が準備すべきこと
インボイス制度導入にあたって、経理があらかじめ準備しておくべきことを4つご紹介します。
インボイス発行事業者への登録を行う
インボイスを交付するためには、納税地を所轄する税務署長からインボイス発行事業者として登録を受ける必要があります。
元々課税事業者だった場合は、納税地を所轄する税務署長に対して適格請求書発行事業者の登録申請書を提出します。
登録申請書の提出方法は郵送とe-Taxを利用する方法の2パターンあります。
郵送の場合、税務署の窓口で申請書の交付を受けるか、国税庁の公式ホームページなどからダウンロードおよびプリントアウトして申請書を手に入れます。
登録申請書には以下の項目を記載します。
- 申請者の住所または居所(法人の場合は本店または主たる事務所の所在地)
- 申請者の納税地
- 申請者の氏名(法人の場合は代表者氏名)または名称
- 法人番号(法人のみ)
- 事業者区分
- 税理士署名(税理士に依頼した場合)
- 登録要件の確認(該当する項目をレ印でチェック)
5の事業者区分は、申請時点の事業形式によってレ印を付ける場所が異なります。それぞれのケースは以下の通りです。
| 事業の形態 | 事業者区分 |
|---|---|
| 課税事業者である場合 | 課税事業者 |
| 免税事業者である場合 | 免税事業者 |
| 新たに事業を開始(設立)し、事業開始の初日から登録を受けようとする場合(※1) | 事業を開始した日の属する課税期間の初日から登録を受けようとする事業者 |
| 新たに事業を開始(設立)する課税事業者(※1以外) | 上記以外の課税事業者 |
| 新たに事業を開始(設立)する免税事業者(※1以外) | 上記以外の免税事業者 |
個人事業主の場合は登録申請書にマイナンバーカードなどの本人確認書類の写しを添付し、管轄の税務署のインボイス登録センター宛に送付します。
一方、e-Taxを利用する場合は、事前にマイナンバーカードなどの電子証明書が必要になります。
パソコンから登録申請する場合はe-Taxのソフトかブラウザ版のe-Taxソフト(WEB版)を、スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末を利用する場合は、e-Tax(SP版)をそれぞれ使用します。
どちらもマイナンバーカードを使ってログインし、利用者識別番号を取得してから登録申請データを作成することになります。登録申請データに入力する項目は書面と同じです。
e-Taxを利用して登録申請した場合、登録通知データを電子データで受け取るかどうかを選択できます。データの方が受け取るまでの期間が短くなります。
また、登録通知の紛失リスクがないこと、取引先宛のメールに登録通知のデータを添付すれば登録番号を容易に通知できる、などのメリットがあるため、国税庁ではe-Taxでの登録手続きを推奨しています。
なお、登録申請の時点で免税事業者である場合、本来であれば消費税課税事業者選択届出書を提出し、課税事業者になる必要があります。なぜなら、インボイス発行事業者として登録できるのは課税事業者に限られているからです。
しかし、令和5年10月1日~令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に関しては、登録申請に関する経過措置の適用により、届出書を提出しなくてもインボイスの登録を受けることが可能となっています。[注5]
[注5]国税庁:インボイス制度において事業者が注意すべき事例集 P2
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023007-071.pdf(参照2023/12/15)
取引の状況を整理する
インボイス制度導入後は、仕入税額控除が適用される取引と、そうでない取引に二分されます。
インボイス発行事業者と、そうでない事業者を明確に区分し、請求書の取り扱いを混同しないよう注意しましょう。
なお、取引の中にはインボイスの交付を免除されるケースや、適格簡易請求書が交付されるケースもあります。
適格簡易請求書とは、別名簡易インボイスと呼ばれるもので、通常のインボイスとは異なり、請求書の交付を受ける事業者の氏名または名称の省略を認めるものです。
簡易インボイスは、小売業や飲食店業、タクシー業など、不特定多数の人に商品やサービスの提供を行う事業者にのみ交付が認められています。
簡易インボイス発行事業者との取引に関しては、請求書の交付を受ける事業者の氏名または名称がなくても正式なインボイスとして認められるので、通常の免税事業者との取引と混同しないよう注意が必要です。
インボイスの保存方法を決める
インボイスは国税関連の書類に該当するため、その事業年度の確定申告の提出期限の翌日から7年間にわたって保管することが義務づけられています。
インボイスは紙で保存することも可能ですが、7年間にわたって保管するとなると収納スペースがかさみますし、後から必要なインボイスを閲覧・確認したい場合に手間と時間がかかります。
インボイスは電子保存が可能なので、省スペースや業務効率化を目指すならインボイス対応のシステムを導入した方がよいでしょう。
なお、電子データとして受け取ったインボイスは電子帳簿保存法に則って保存する必要があります。
電子データでインボイスをやり取りする場合は、電子帳簿保存法に対応したシステムの導入を行いましょう。
今後の取引の見直し
インボイス制度導入後もインボイスを発行できない免税事業者と取引する場合、消費税の仕入税額控除を適用することができません。
同じ免税事業者と取引した場合でも、制度導入前に比べて請求書の受領側の負担が大きくなります。
当初6年間は免税事業者との取引でも80%ないし50%の仕入税額控除が適用されますが、満額を仕入控除できるインボイス発行事業者との取引に比べると負担が大きくなるのは否めません。
負担を減らしたい場合は、当該免税事業者と話し合いをし、今後の取引について交渉する必要があります。
ただし、相手方に対して自社が有利な立場にある場合、一方的に価格の値下げを要求したり、インボイス発行事業者に移行することを強要したりすると、独占禁止法に抵触するおそれがあります。
取引条件の見直しおよび交渉自体は問題ありませんが、優越的立場を濫用することは違法となるので注意しましょう。
インボイス制度に合わせて経理業務を効率化するポイント
インボイス制度に合わせて経理業務を効率化する場合に押さえておきたいポイントを2つご紹介します。
インボイス制度に対応したシステムを導入する
インボイス制度に対応したシステムやソフトを導入すれば、インボイスの作成や発行を手軽に行えます。プリインストールされているテンプレートを利用すれば、インボイスに必要な事項を漏れなく記載できるので、記入漏れやミスのリスクを低減できます。
インボイスを受領する際も、相手がインボイス発行事業者であるかどうかを自動でチェックしたり、必要事項が不備なく記入されているかどうかを確認したりできます。
インボイスとそうでない請求書の仕訳支援も行えるほか、受領したインボイスを電子データとして取り込み、保存することもできるので、紙のインボイスを取り扱うよりも業務を効率化できます。
電子インボイスを導入する
電子インボイスとは、電子データ化したインボイスのことで、別名デジタルインボイスと呼ばれています。
インボイスの作成や発行、送付、保管に至るまで、すべてのプロセスを電子データで行えるところが特徴です。
紙をいちいち発行したり、ファイリングしたりする手間を省けるため、時間とコストの節約にも役立ちます。
電子インボイスならテレワークにも対応しやすいため、多様な働き方を採用している企業は電子インボイスの導入を検討してみるとよいでしょう。
インボイス制度に対応できる経理業務の体制を整えよう
インボイス制度導入後の経理業務は、これまでとは異なる形式の請求書(インボイス)を発行・受領したり、消費税の計算を変更したりと、さまざまな対応に追われることになります。
従来通りの方法で業務を行うと、正式なインボイスとして認められなかったり、消費税の仕入税額控除が適用されなかったりと、いろいろなトラブルが生じる原因となります。
インボイス制度に対応するためにも、制度導入後にどのような変化が生じたのか、どのような準備をすべきかをしっかり把握しておきましょう。